2010年05月
「マリア」と「カルメン」——— ともに、スペインではごく一般的な女性の名である。この名前が与えるイメージには、<女>というものの二つの面があらわれている。すなわち、「マリア」から連想されるのは、カトリック国であるスペインで昔から崇拝されてきた汚れなき聖母マリア。そして「カルメン」といえば、ビゼーのオペラでも有名なメリメの小説『カルメン』の奔放な主人公。いずれも美しく、男性が憧れる女性像を象徴する人物だが、どちらもスペインと関わりがあるというのは何やら気になってしまう。
ともあれ、世の殿方たちは大なり小なり、一方では「母のような愛に守られたい」と夢を見、もう一方では、「悪い女に翻弄されてみたい」という願望を持っているのではないだろうか。なんとも欲張りなものだが、オトナの女はそんなことで目くじらを立ててはいけない。男って、しょうがないわね・・・と、余裕で微笑みながら見守って(見張って)いればいいのである。そういえば、男を適度に振り回してくれる「ツンデレ」(*万が一、知らない方は「現代用語の基礎知識」「知恵蔵」などをご参照あれ)というキャラは、そんな願望を叶えるのにかなりいい線をついているのかもしれない。まぁツンデレくらいで収まっていればよいのだが、実際カルメンのような“ファム・ファタルな女”に出会ってしまったら終わりだ。思いのままにならない女ほど独占したくなるのが常であり、ファム・ファタルが男に束縛されることほど似合わないものはない。かくして、そんな女につかまった男の行く末には、破滅しか残されていないのである…
『カルメン』は、セビーリャのたばこ工場で働くジプシーの女カルメンと、彼女に恋して人生を狂わせてしまう真面目な衛兵伍長ドン・ホセをめぐる物語。このオペラを作曲したビゼーはフランス人だが、音楽は生き生きとしたスペインの色彩にあふれ、そのころ流行りの「似非スペイン趣味」とは一線を画している。カスティーリャで発祥しアンダルシアでも広まったセギディーリャス、アラゴン地方のホタ、キューバから入ったハバネラなど、スペインの代表的な民俗音楽が素材に使われ、世界にスペイン音楽の魅力を伝えてくれている定番オペラだ。
さて「スペイン音楽の魅力は何?」と問われたならば、まず「生身の人間が感じられるところ」と答えることができる。ここでいう「スペイン音楽」とは、クラシック音楽としてのものだが、スペインの音楽は、いわゆる「西洋音楽」とはちょっと違った道をたどっている。クラシック音楽の主流はおもにカトリックの教会と深くかかわって発展していったのだが、スペインでは、8世紀初頭からほぼ7世紀にわたってイスラム支配を経験した歴史や、もともと豊富だった民俗音楽・舞踊のエッセンスなどがクラシックの世界に入りこんだことで、他の国には見られない独自の個性が培われたのである。そして「民俗音楽」はまさに民衆の内から自然に発するものだから、理屈抜きの人間的な感情が息づく。そこには喜怒哀楽を素直に吐露する歌があり、踊りがあり、男がいて、女がいる。そして、そこに生まれる「愛と死」の様々なドラマ。そんなスペイン的といえるテーマがわかりやすく盛り込まれているのが、『カルメン』なのである。
カルメンが歌う有名なハバネラ、『恋は野の鳥』はコケティシュだ。この曲、実はイラディエルというスペイン人作曲家が作曲したものだったのだが、民謡だと思いこんでいたビゼーはその旋律をそのまま使ってしまい、意図せずして「盗作」になってしまった、というオチつきの歌である。ちなみにハバネラ(=ハバナ風)という曲種の元をたどると、意外にもイギリスのカントリーダンスに行き着く。ロココ趣味に飽きたマリー・アントワネットがイギリスのカントリーダンスにはまり、フランス風に「コントルダンス」と呼ばれて流行ったのだが、それが当時フランスの植民地だったハイチにわたり、さらに1791年のハイチ革命からの避難民がキューバに持ちこみ、この地で影響を受けて変化し「ハバネラ」となった、という興味深くも長いヒストリーがあるのだが、さらにこれが船乗りによってスペインにもたらされて大ヒットしたために、スペイン舞曲のひとつという認識で広まったのだった。
ハバネラの特徴は、キューバで加わったとされる揺れるようなリズムだが、『恋は野の鳥』のメロディ冒頭は、その魅惑的な伴奏にのって、高い音から半音ずつ下がってくる。艶めかしい、いわば「誘惑の音型」である。このダブル・パンチ、いや、歌うカルメン自身の魅力も加わってのトリプル・パンチに男たちはノックアウトされるのだが、ドン・ホセだけは興味を示さない。この態度が逆にカルメンの気をひき、ファム・ファタル心(そんなものがあればの話だが)に火をつけてしまったのか、もしくは、彼が気持ちを偽っていることを見抜き、その仮面をはがしてやろうと思ったのだろうか。カルメンは胸につけていた花をホセに投げつけて去り、その花を手にとったホセは心を乱す。タイトルの「恋は野の鳥」とは、恋はまるで空を飛ぶ鳥のように気まぐれで、思い通りにはならないもの、という意味だが、この「恋」はそのまま「カルメン」に置き換えることができるし、ご親切にも本人が「私に思われたなら、あぶないわよ!」と歌って忠告しているのに、理性に反して惹かれてしまうホセ君。さもありなん、心理学的にいえば、この言い方は逆に効果的な、高度な恋のテクニックなのである。作戦成功、ウブな彼は見事に「ひっかかった」のだ。
しかしホセはどこか優柔不断で、突っ走りきることができない。そんな彼に愛想を尽かし、闘牛士エスカミーリョに心が移ったカルメンは、やり直してくれとすがってきたホセを拒絶。激昂したホセはカルメンの胸に短剣を突きたてる。崩れ落ちるカルメンを抱いて号泣するダメ男代表・ホセを見て、観客は「あ〜あ、だから言ったのに!」と思うわけである。
そして「たとえ短くても、あんなドラマティックな生き方をしてみたい!・・・とは思うけど、こんな風に終わるのなら、やっぱりワタシって、平凡だけど幸せなのだわ!」
ここにカタルシス実現。観客を満足させ娯楽としてのオペラの役割もしっかり果たしている『カルメン』は、やはり名作である。
カルメンはしばしばスペイン女性の典型的タイプのようにいわれるが、スペインの女性がみな「カルメン型」だったら大変である。それに、彼女は「ファム・ファタル」としては果たしてどうなのだろうか。純粋でまっすぐ過ぎるゆえに身を滅ぼしたのなら、悪女としての出来は不完全なんじゃないだろうか。考えてみれば、ドン・ホセも馬鹿ならカルメンも馬鹿である。不器用ともいえるかもしれない。しかし、心の自由を守ったことによって命を落とすことになったとしても、彼女はそんな生き方を後悔などしていないのだろう。
自分に正直に生きる、というのはまさにスペイン的。その意味では、確かにカルメンはスペイン女性の一面を表しているといえるかもしれない。しかし実際に、“ジプシー社会に生きる女”がこんなことをしでかしたら大変なことになるようである。心変わりし夫を裏切った女は文字通り世界の果てまで追いかけられるという実例を、ヒターノ(スペイン語でジプシーの意味)と交流のあるスペイン人の友人に聞いたことがあるが、こうなると「自分に正直」もまさに命がけだ。もっとも、命すら賭けられるのが本当の恋というものかも。
さて「スペイン男」として連想される人物の筆頭は、やはり「ドン・フアン」だろう。何しろ世界にとどろく女たらしの代名詞、このイメージによりスペインの男性は少々迷惑を被っているかもしれないので、「実際の一般スペイン人男性はもっと素朴で、大変誠実な方々である」と声を大にして擁護しておこう。(ついでにドン・フアン氏をも擁護するならば、彼は狩人的なカサノヴァとは違い、“ただ一人の女”を追い求めた結果女性を遍歴した男である。)けれど中には、前述ドン・ホセのように、嫉妬深くて思い切りの悪い殿方も・・・。
というところでもう一人思い浮かぶのが、マヌエル・デ・ファリャ作曲、マルティネス・シエラ脚本によるバレエ『恋は魔術師』に出てくる男である。スペイン近代を代表する作曲家であるファリャはフラメンコ、特にカンテ・ホンドに惹かれていたが、この作品の舞台もグラナダのジプシー社会に設定されていて、フラメンコ的な雰囲気が漂っている。
この場合何が「魔」なのかというと、ズバリ「男」なのである。『四谷怪談』のお岩、『牡丹灯籠』のお露、『番町皿屋敷』のお菊・・・日本の場合、化けて出てくるのは女とたいがい相場が決まっている。しかし、この作品では死んだ男が嫉妬に狂い、亡霊となってあらわれる。そんな男の幽霊というのもなかなか怖そうだ。そしてこの男の名が、これまた「ホセ」なのである(単なる偶然だ。そうに違いない。全世界のホセさん、お許しを!)。
夫ホセの死後、新しい恋人ができたカンデラは、邪魔をする夫の亡霊を美しい友人女性に誘惑させ、晴れて新しい恋を成就させるのだが、このカンデラもまた、“現在を生きる”女だ。過去は、振り返っても仕方がないのである。そもそも「過去」は「現在」がつくるもので、「未来」は「現在」の延長線上にある。何もかも現在次第なのであれば、「今に生きること」に集中するのが一番簡単で、正統な方法ではある。
しかし、古来より日本的美徳において讃えられるのは「待つ女」かもしれない。「進む女」も強いが、「待ち続ける女」も相当のツワモノである。お国柄によりタイプの差あれど、つまるところ「女は強し」か。
ちなみに、ファリャ自身は敬虔なカトリック信者で、修行僧のような生活をして音楽活動に没頭、生涯独身を通している。ファリャとその音楽をめぐってのお話は、次の機会に。
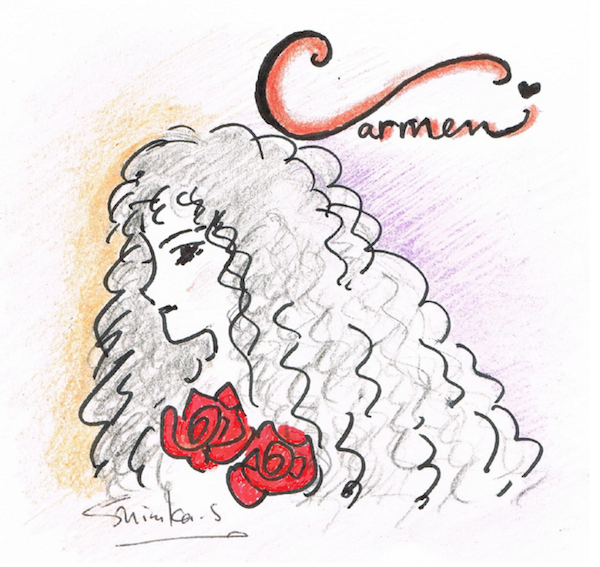
下山 静香 / Shizuka Shimoyama
桐朋学園大学卒。99年、文化庁派遣芸術家在外研修員として渡西、マドリード、バルセロナほかで研鑽。NHK-BS、Eテレ、フランス国営ラジオなどに出演。海外アーティストとの共演多数。CD《ゴィエスカス》《ショパニアーナ》など10枚、共著は10冊以上を数える。翻訳書『サンティアゴ巡礼の歴史』。2015年より「下山静香とめぐるスペイン 音楽と美術の旅」ツアーシリーズを実施。桐朋学園大学、東京大学 非常勤講師。日本スペインピアノ音楽学会理事。
www.facebook.com/shizukapianista17
裸足のピアニスト・下山静香のブログ ameblo.jp/shizukamusica
★ ニューアルバム《Alma errante 〜 さすらいの魂》中南米ピアノ名曲コレクションⅡ・アルゼンチン10/4演奏会にて先行販売、11月正式リリース!















